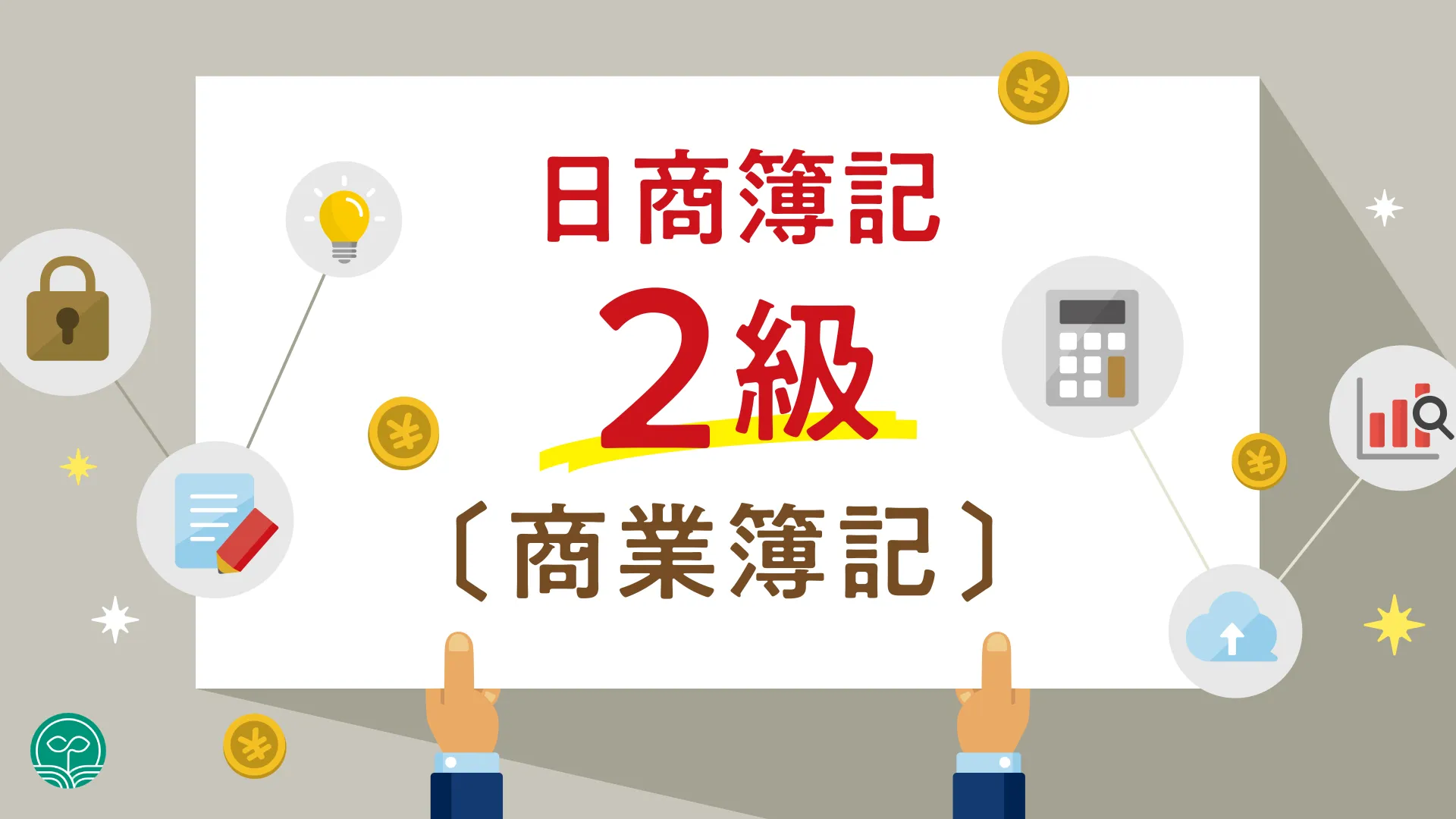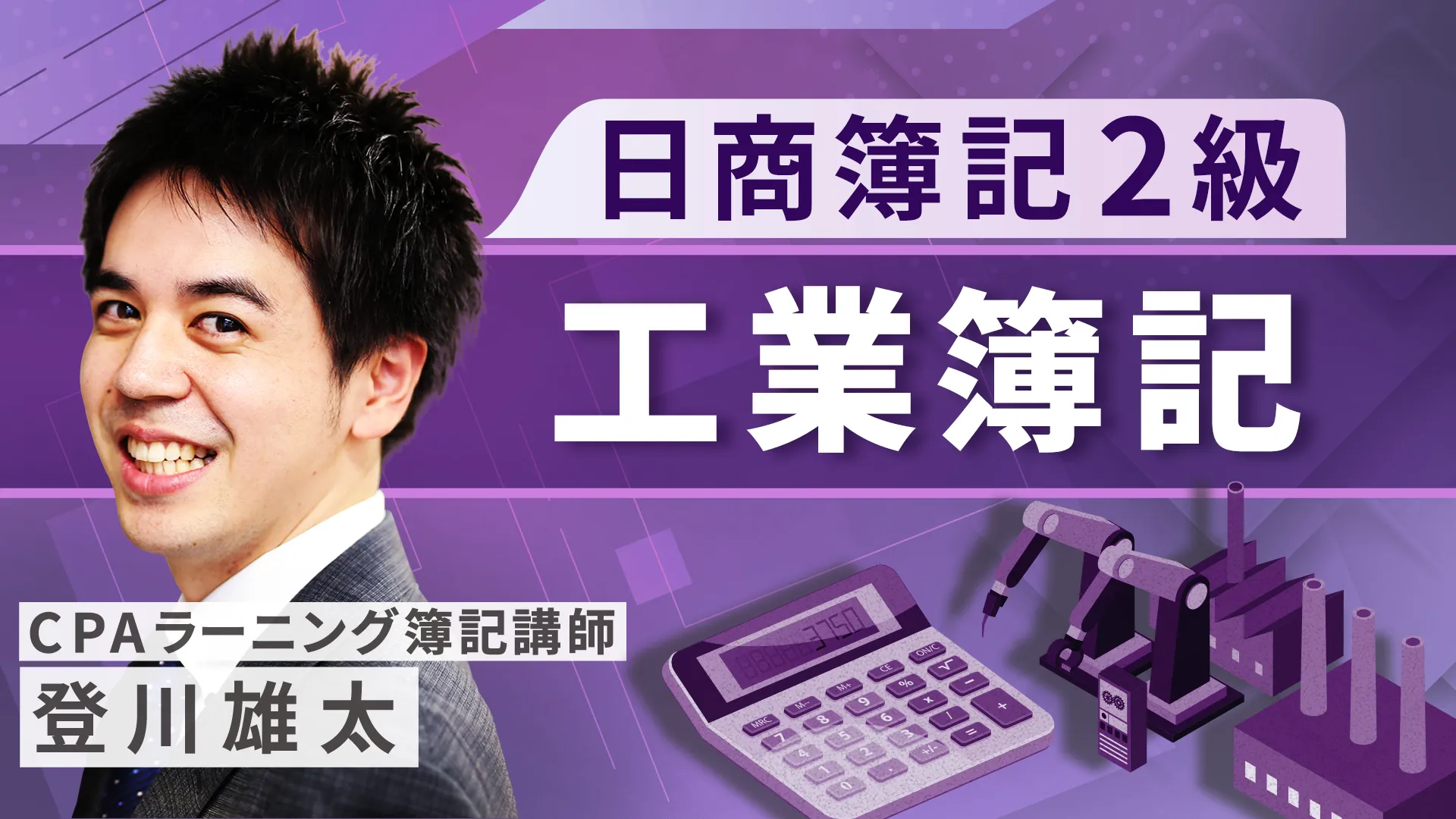「簿記2級とはどのような資格なの?取得するべきか迷っている」
「簿記2級とはどのようなことを学ぶの?仕事に活用できる?」
ビジネスに役立つ資格として人気がある簿記2級。
聞いたことはあるものの「どのようなスキルが身につくのか」「どのように活用できるのか」気になりますよね。
簿記2級とは商業簿記と工業簿記の両方を学び企業の財務諸表作成・経営管理ができる知識を身につける資格です。

簿記3級よりも専門性が高いため、会計や経理への就職・転職に有利になる傾向があります。
そのため、とくに下記のようなケースでは、簿記2級のメリットを最大限に活用できるでしょう。
簿記2級が自分に合う資格なのか、将来自分の仕事に役に立つ資格なのか見極めるためにも、簿記2級がどのような資格なのか理解しておきましょう。
そこでこの記事では、簿記2級の概要や難易度、試験内容、取得メリットなど簿記2級に関する基礎知識をご紹介します。
後半では試験勉強のポイントにも触れているので、簿記2級にチャレンジしてみようと思った方は是非ご一読ください。
| この記事を読むと分かること |
| ・簿記2級の概要が分かる ・簿記2級の難易度や合格率が分かる ・簿記2級の試験範囲が分かる ・簿記2級と3級、1級の違いが分かる ・簿記2級を取得するメリットが分かる ・簿記2級の取得が向いている人が分かる ・簿記2級の試験方法や試験日程が分かる ・簿記2級の試験勉強のポイントが分かる |
この記事を最後まで読めば簿記2級とはどのような資格なのか理解でき、簿記2級の取得が自分の目的に合うのかを確認することができます。
簿記2級は難易度と専門性のバランスが良く比較的挑戦しやすい資格なので、ぜひ参考にしてみてください。
登録者が70万人を突破したCPAラーニングでは、プロの講師による簿記2級(全範囲)の講義が【完全無料】で受けられます。
公式アプリではオフライン再生もできるので、隙間時間に活用することも可能です。
※テキスト・講義動画・問題集・模擬試験・試験対策などの動画コンテンツが全て無料・見放題なので独学で学びやすい!
目次
1.日商簿記2級とは
| 日商簿記2級 会計や経理の知識を深める資格 | |
| 特徴 | 商業簿記と工業簿記の両方を学び企業の財務諸表作成・経営管理ができる知識を身につける日商簿記3級よりも専門的で深い知識が求められる |
| 出題範囲 | 商業簿記:一般的な企業での会計処理方法 工業簿記:製造業の会計処理方法 |
| 平均合格率 | 約30%難易度は比較的高い |
| 試験方法 | 統一試験・ネット試験・団体試験 |
| 勉強時間の目安 | 250時間 |
| 就職・転職への活用度 | 会計や経理関係の仕事に就職・転職したい場合に有利になる |
| おすすめの人 | 会計や経理をメインとする仕事がしたい人日商簿記1級や公認会計士・税理士などの上位資格を目指したい人大学入試で優遇を受けたい人 |
| 資格の価値 | 日商簿記3級よりも希少価値がある |
日商簿記2級とは、商業簿記と工業簿記の両方を学び企業の財務諸表作成・経営管理ができる知識を身につける資格です。
日商簿記3級では企業のお金の流れを財務諸表に記録する知識を中心に学びますが、日商簿記2級ではそこから一歩進み帳簿記入だけでなく経営管理する知識も学びます。
つまり、日商簿記2級までを取得すると、財務諸表の作成と経営管理の双方が理解でき会計や経理業務の即戦力として活躍できるようになります。
| 知識 | 概要 | 実際の業務例 |
| 財務諸表の作成 | ルールに沿って企業の経営状態や財務状況を明確にする財務諸表を作成できる (貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書など) | ・日々の帳簿記録 ・決算書の作成補助 |
| 経営管理 | 財務諸表を分析して企業の課題や目標を達成するにはどうすればいいのか検討できる | ・企業の経営課題を見つける ・部門ごとの改善や評価を行う |
昨今の企業は簿記の基礎知識だけでなく、経営管理に関する専門的なスキルも求める傾向があります。
日商簿記2級を取得すると会計や経理に関する専門的なスキルを有する証となり、就職・転職に有利になるでしょう。
| 日商簿記2級を取得するとできること・できないこと | |
| できること | ・中小企業の会計や経理の実務に活用できる ・会計や経理への就職・転職に有利になる |
| できないこと (日商簿記1級が必要) | ・大企業の会計や経理に活用できる専門性は取得できない ・税理士試験税法科目の受験資格は取得できない |
日商簿記2級は簿記の基礎知識から一歩踏み込み会計や経理の業務で役立つ専門的なスキルを身につける資格なので「会計や経理の仕事に就きたい」「キャリアアップを目指したい」という場合におすすめです。
▼日商簿記2級については下記の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。
簿記2級はどんな資格?必要な勉強時間や合格率、勉強方法も紹介
| 【簿記検定には3種類ある!日商簿記が主流】 簿記検定には下記の3種類があり「日商簿記」の受験が一般的です。 ・日商簿記:学生・社会人向けの一般的な資格 ・全経簿記:主に経理や会計の専門学生向けの資格 ・全商簿記:主に商業科の高校生向けの資格 この記事では、日商簿記の2級について詳しく解説します。 3種類の簿記検定の違いは下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。 【日商簿記、全商簿記、全経簿記の違いとは?】〜ネット試験などの最新情報もご紹介します!〜 |
2.日商簿記2級の平均合格率は約30%!比較的難易度が高い
日商簿記2級の平均合格率は約30%です。
10人中3人程度しか合格できないため、比較的難易度が高いと言えるでしょう。
ここでは、統一試験とネット試験それぞれの直近の合格率を詳しく解説しています。
日商簿記2級の難易度を理解するためにも、参考にしてみてください。
| 日商簿記3級の平均合格率 | 約30% |
| 統一試験 (過去10回の平均合格率) | 20.45% |
| ネット試験 (2020年12月~2023年12月までの平均合格率) | 39.7% |
2-1.統一試験の合格率
統一試験(試験会場に集合して実施するペーパー形式の試験)の過去10回の平均合格率は20.45%です。
過去5回の合格率を見ると、合格率30%以下を推移しています。
| 統一試験(ペーパー形式の試験)の合格率 | |||
| 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 165回(2023年11月19日実施) | 9,511名 | 1,133名 | 11.9% |
| 164回(2023年6月11日実施) | 8,454名 | 1,788名 | 21.1% |
| 163回(2023年2月26日実施) | 12,033名 | 2,983名 | 24.8% |
| 162回(2022年11月20日実施) | 15,570名 | 3,257名 | 20.9% |
| 161回(2022年6月12日実施) | 13,118名 | 3,524名 | 26.9% |
日商簿記2級は出題範囲が広く深い理解が求められる問題が多いので、難易度が高くなる傾向があります。
また、日商簿記2級には受験資格がないため、十分に試験勉強をしていない人や会社や学校で強制的に受験している人も含まれています。
そのため、試験勉強の姿勢に差が出やすく、合格率にも影響を及ぼしていると考えられています。
▼日商簿記2級の合格率が低い理由は下記でも触れているので、参考にしてみてください。
日商簿記2級の合格率はなぜ低下しているのか?その意外な攻略法とは
2-2.ネット試験の合格率
商工会議所が指定した試験会場でパソコンを使用して受験するネット試験の2020年12月~2023年12月までの平均合格率は39.7%です。
過去4年の合格率は37~46%程度をキープしていて、統一試験よりも合格率が高いことが分かります。
| ネット試験の合格率 | |||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 2023年4月~2023年12月 | 78,980名 | 29,188名 | 37.0% |
| 2022年4月~2023年3月 | 105,289名 | 39,076名 | 37.1% |
| 2021年4月~2022年3月 | 106,833名 | 40,713名 | 38.1% |
| 2020年12月~2021年3月 | 29,043名 | 13,525名 | 46.6% |
参考:日本商工会議所「2級・3級受験者データ(ネット試験)」
統一試験とネット試験では難易度は同じであるものの、下記のような理由からネット試験のほうが合格率が高くなっていると考えられます。
| 【ネット試験のほうが合格率が高い理由】 ・記述問題が選択式で解答する形式になっている ・ネット試験はランダムに出題されるので難易度が安定しやすい ・ネット試験に対応し試験時間が短縮され、問題数が適切に調整されている。 |
▼ネット試験の合格率が高い理由は下記の記事でも触れているので、参考にしてみてください。
統一試験(筆記試験)とネット試験どちらが受かりやすい? ~会計士が直近の合格率から考察~
▼日商簿記2級の難易度は下記の記事でも触れているので、参考にしてみてください。
簿記2級の難易度とは?独学で合格可能なのか、合格率なども紹介
3.日商簿記2級の試験範囲一覧
簿記2級の試験範囲は「商業簿記」と「工業簿記」です。
商業簿記は、一般的な会社や店舗で使用する会計処理方法です。
工業簿記は製造業の会社処理方法のことで、日商簿記2級から試験範囲に追加されます。
商業簿記と工業簿記それぞれの試験範囲は下記のとおりです。
| 項目 | 商業簿記の具体的な出題範囲 |
| 簿記の基本原理 | 基礎概念・取引・勘定・帳簿などの簿記の基本的な考え方や用語を理解する ●2級からの追加項目 ・純資産と資本の関係 ・記帳内容の集計・把握 |
| 諸取引の処理 | 売掛金や買掛金、手形、税金など簿記に必要な取引の処理方法を理解する ●2級からの追加項目 ・有価証券 ・銀行勘定調整表 ・収益認識 ・営業外支払(受取)手形 ・債務の保証 ・有形固定資産の除却、廃棄 ・無形固定資産など |
| 決算 | 決算時の精算方法などを理解する ●2級からの追加項目 ・その他有価証券評価差額金 ・財務諸表の区分表示など |
| 株式会社会計 | 主に純資産の会計処理に必要な知識を理解する ●2級からの追加項目 ・資本剰余金 ・任意積立金 ・準備金積立額の算定 ・会社の合併など |
| 2級からの項目 本支店会計 | 企業が本社以外に支店を設けたときの会計処理を理解する ・本支店会計の意義・目的 ・本支店間取引の処理など |
| 2級からの項目 連結会計 | 連結財務諸表の記録方法を理解する ・非支配株主持分 ・のれん ・連結会社間取引の処理など |
| 項目 | 工業簿記の具体的出題範囲 |
| 工業簿記の本質 | ・工業経営の特質 ・工業簿記と原価計算 ・原価計算基準 ・工業簿記の種類など |
| 原価 | ・原価の意義 ・原価の要素、種類、態様 ・直接費と間接費 ・実際原価と予定原価 ・製品原価と期間原価など |
| 原価計算 | ・原価計算の種類と形態 ・実際原価計算と予定原価計算 ・個別原価計算と総合原価計算 ・全部原価計算と直接原価計算 ・原価計算の手続など |
| 工業簿記の構造 | ・勘定体系 ・帳簿組織 ・決算手続 ・財務諸表 |
| 材料費計算 | ・材料費の分類 ・消費量の計算 ・購入原価の計算など |
| 労務費計算 | ・労務費の分類 ・消費賃金の計算 ・支払賃金、給料の計算など |
| 経費計算 | ・経費の分類 ・経費の計算など |
| 製造間接費計算 | ・製造間接費の配賦計算 ・固定予算と変動予算 ・配賦差異の原因分析 ・配賦差異の処理など |
| 部門費計算 | ・部門費計算の意義と目的 ・原価部門の分類 ・補助部門費の製造部門への配賦など |
| 個別原価計算 | ・個別原価計算の意義 ・製造指図書と原価計算表 ・仕損費の処理など |
| 総合原価計算 | ・総合原価計算の意義と種類 ・単純総合原価計算の方法と記帳 ・等級別総合原価計算の方法と記帳 ・組別総合原価計算の方法と記帳など |
| 標準原価計算 | ・標準原価計算の意義と目的 ・標準原価計算の方法と記帳 ・標準原価差異の原因分析など |
| 売上・原価・利益関係 の分析 | ・貢献利益の計算 ・損益分岐図表 ・損益分岐点等の計算 |
| 固変分解 | ・費目別精査法 ・高低点法 |
| 直接原価計算 | ・直接原価計算の意義と目的 ・直接原価計算の方法と記帳など |
| 製品の受払い | ・製品の販売と記帳 ・製品の受入れと記帳 |
| 営業費計算 | ・営業費の意義 ・営業費の分類と記帳 |
試験範囲を見ると分かるように日商簿記2級は商業簿記と工業簿記の基礎知識にとどまらず、実務で使える記帳方法や仕訳方法など一歩進んだ深い知識が求められます。
また、製造業などを中心に必要な原価計算や利益分析の知識も身につきます。
日商簿記2級の出願範囲は毎年度4月1日に施行されている法令等に準拠して改正されるため、最新の出願範囲を確認するようにしましょう。
▼日商簿記3級の出願範囲は下記で解説しています。日商簿記3級の出願範囲は日商簿記2級に含まれているので、参考にしてみてください。
簿記3級とは
4.日商簿記3級・1級との違い
日商簿記2級の概要が理解できたところで、3級や1級との違いが気になりますよね。
簡単に言うと日商簿記3級は簿記の基礎知識を確認する入門資格で、日商簿記1級はスペシャリストとして活躍できる専門的なスキルを要する資格です。
階級により難易度や出願範囲、おすすめの人が異なるため、事前に確認しておきましょう。
| 項目 | 日商簿記3級 | 日商簿記2級 | 日商簿記1級 |
| 概要 | 簿記の基礎知識を学ぶ入門資格 | 会計や経理の仕事で役立つ専門的なスキルを身につける資格 | 会計や経理のスペシャリストとして活躍できる専門性の高い資格 |
| 出題範囲 | 商業簿記 | 商業簿記・工業簿記 | 商業簿記・工業簿記・会計学・原価計算 |
| 合格率 | 約40% | 約30% | 約10% |
| 難易度 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 勉強時間の目安 | 100~150時間 | 250時間 | 500~2,000時間 |
| 就職・転職への活用度 | |||
| おすすめのケース | ビジネスシーンで役立つ簿記の基礎知識を学びたい人 | 会計や経理の仕事で使える専門的なスキルを身につけたい人 | 会計や経理のスペシャリストとして活躍したい人 |
4-1.【基礎知識レベル】日商簿記3級との違い
日商簿記3級は、簿記の初心者向けの入門資格です。
簿記の概要や小規模企業の帳簿記入の基礎知識を学びます。
| 日商簿記3級 | |
| 特徴 | ・簿記の初心者が受ける入門資格 ・帳簿記入の基礎が身につく ・経理や会計職に限定しないでビジネスパーソンが持つべき経営活動の基礎知識を学べる |
| 出題範囲 | 商業簿記のみ |
| 平均合格率 | 約40% 難易度は比較的低い |
| 試験方法 | 統一試験・ネット試験・団体試験 |
| 勉強時間の目安 | 100~150時間(独学で目指せる) |
| 就職・転職への活用度 | 有利になるケースもあるが上位資格と比較すると劣る |
| おすすめの人 | ・簿記を学習したことがない人 ・幅広いビジネスで役立つ資格を取得したい人 ・入学したい大学に日商簿記3級での優遇がある人 |
| 資格の価値 | 合格率が高く資格保有者が多いため上位資格のような希少価値はない |
日商簿記2級との大きな違いは、出題範囲と合格率です。
日商簿記3級は簿記の基本となる商業簿記の帳簿記入を中心に学びます。
中小企業のお金の流れを理解して、ルールに従って財務諸表を作成する知識を身につけます。
一方、日商簿記2級は商業簿記と工業簿記の帳簿記入・経営管理を学びます。
一般的な企業の帳簿記入だけでなく製造業の帳簿記入も出題範囲になるので、異なるルールや仕訳を理解しなければなりません。
また、経営管理の知識も学ぶので、財務諸表を分析して経営に活かせるスキルも身につけます。
| 資格 | 試験対象となる範囲 |
| 日商簿記3級 | 簿記の基本となる商業簿記の帳簿記入を中心に学ぶ →中小企業を対象にルールに沿って帳簿を作成できる |
| 日商簿記2級 | 商業簿記と工業簿記の帳簿記入・経営管理を学ぶ →一般的な企業・製造業を対象に帳簿記入・経営管理ができる |
このように、日商簿記3級と日商簿記2級では身につけるスキルが異なるため、難易度や勉強時間も変わります。
日商簿記3級は簿記の基礎知識を学ぶ資格で、日商簿記2級は会計や経理などの実務でより活用できる応用知識を学ぶ資格だと言えるでしょう。
▼日商簿記3級の概要は下記の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。
簿記3級はどんな試験?必要な勉強時間やネット試験についても解説
4-2.【スペシャリスト】日商簿記1級との違い
日商簿記1級は、会計や経理のスペシャリストとして2級よりも更に踏み込んだ深い知識を求められる資格です。
商業簿記と工業簿記の知識に加えて、会計や原価計算などの企業会計に関する法規も学びます。
| 日商簿記1級 | |
| 特徴 | ・非常に難易度が高く深い会計の知識が求められる ・会計や経理のスペシャリストとして活躍できるレベルの知識が問われる ・合格すると税理士への受験資格を得られる |
| 出題範囲 | 商業簿記・工業簿記・会計学・原価計算 |
| 平均合格率 | 約10.9%難易度は高い |
| 試験方法 | 統一試験のみ |
| 勉強時間の目安 | 500~2,000時間(独学は難しい) |
| 就職・転職への活用度 | 希少価値が高く上場企業の経理部・財務部・税理士事務所・監査法人など高度な知識を活かした業界を検討できる |
| おすすめの人 | ・会計や経理のスペシャリストを目指す人 ・公認会計士、税理士などの上位資格を目指す人 |
| 資格の価値 | 難易度が高いので希少価値がある |
日商簿記2級との大きな違いは、出題範囲と難易度です。
日商簿記1級では帳簿記入・経営管理のより専門的な知識に加えて、会計基準や会社法などを理解し法規に沿って経営管理や経営分析をするスキルを身につけます。
日商簿記2級よりもさらに専門的な知識を習得できるため、会計や経理のスペシャリストとして大企業や大規模な税理士事務所などで勤務することも検討できるでしょう。
| 資格 | 試験対象となる範囲 |
| 日商簿記1級 | 帳簿記入・経営管理のより専門的な知識に加えて、会計基準や会社法などを理解し法規に沿って経営管理や経営分析をする知識を学ぶ →大企業や税理士事務所、監査法人で身につけた知識を存分に活かして働ける |
| 日商簿記2級 | 商業簿記と工業簿記の帳簿記入・経営管理を学ぶ →一般的な企業・製造業を対象に帳簿記入・経営管理ができる |
一方で、専門的な知識が求められる分、難易度が高く過去10回(152~165回)の平均合格率は約10.9%です。
10人に約1人しか合格できないレベルなので、勉強に時間をかけて取り組む必要があります。
日商簿記2級にチャレンジをした後に「もっと会計や経理に関する知識を深めたい」「公認会計士や税理士などの上位資格を目指したい」という場合は、日商簿記1級にも挑戦してみる価値はあるでしょう。
▼日商簿記1級については下記の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
簿記1級は意味がない?簿記1級を取得するメリットが大きい人と小さい人について解説!
簿記1級の合格率が知りたい!取得するメリットや勉強時間はどのくらいかかる?
| 【日商簿記1級から受験することもできるが基本的には日商簿記2級合格後にチャレンジする】 日商簿記には受験資格がないのでいきなり日商簿記1級からチャレンジできますが、 実際に1級から受験する人はほとんどいません。 難易度が高いことや日商簿記3級、2級の知識が必要なことから、 3級から順に挑戦する方法が主流です。 日商簿記1級に興味がある場合は、まずは日商簿記2級の知識の習得を目指すことをおすすめします。 |
5.日商簿記2級を取得する4つのメリット
日商簿記の階級ごとの違いが理解できたところで、日商簿記2級を取得するメリットが気になりますよね。
ここでは、日商簿記2級を取得するメリットを具体的にご紹介します。
日商簿記2級を取得すると進学や就職、転職に有利になることがあるので、ぜひチェックしてみてください。
| 日商簿記2級を取得する4つのメリット |
| ・会計や経理の実務に活用できる ・就職・転職に有利になる ・大学入試時に優遇されるケースがある ・上位資格を目指しやすくなる |
5-1.会計や経理の実務に活用できる
簿記2級は、会計や経理の実務に活用できるスキルを取得できます。
日商簿記の階級ごとに取得できるスキルを見てみると、日商簿記2級は難易度と実務への活用度のバランスがいいことが分かるでしょう。
| 階級 | 実務への活用度 |
| 簿記2級 | 帳簿記入と経営管理の双方のスキルを取得できる |
| 簿記3級 | 帳簿記入がメインなので会計や経理のサポートはできるものの実務に使える知識としては弱い |
| 簿記1級 | 会計や経理のスペシャリストとしての活躍が期待できるが難易度が高く勉強時間を要する |
日商簿記3級では帳簿記入の知識がメインなので、会計や経理のサポート業務はできても即戦力としては弱い部分があります。
日商簿記2級は経営管理の知識を問われるため、帳簿記入から一歩進み帳簿の情報を読み取り経営に役立てるスキルを身につけます。
多くの企業の経理では帳簿記入だけでなく経営管理能力も求めているので、日商簿記2級を取得していると「実務に活用できる知識」を保持していると認識してもらえるのです。
実際に日商簿記2級を取得していると帳簿記入と経営管理に関する専門知識があるとみなされるため、経理業務では下記のように年収にも大きな差が出ます。
例えば、30代の一般的な年収と簿記2級取得者の年収を比較すると、74万円もの差があります。
30代の10年間一定の年収を得たと仮定すると、10年で得られる収入に740万円も差がつくのです。
日商簿記2級は会計や経理に携わるうえで必要な帳簿記入と経営管理の双方の知識を保持していることの証明となり、実務で即戦力として活躍できる可能性が高いため、簿記2級取得者の平均年収は一般的な平均年収と比較すると高くなっていると考えられます。
▼企業で日商簿記2級以上が求められる理由は下記でも解説しているので、参考にしてみてください。
【キャリア】企業で求められるのは簿記2級以上?~3級との違いも解説~
【日商簿記2級が実務に役立った声】
| 【日商簿記2級のスキルは経理や会計以外でも役立つ】 「日商簿記2級は経理や会計職以外では役立たないの?」と感じている方もいるかと思います。 会計は「ビジネスの三種の神器」と言われており、どのような業種でも持っていて損はありません。 日商簿記2級のスキルが業務に直結するのは経理や会計職になりますが、 営業職やコンサルタント職、金融業界などでも役に立ちます。 ・営業職やコンサルタント職:営業先企業の財務諸表を分析できるため、数値をもとに説得力のある提案ができる ・金融業界:クライアントの財務諸表を正確に読み取れるので商品やサービスの提案がしやすい 会計や経理に直結しない仕事であっても、 日商簿記2級のスキルを活かして活躍できる場面は多々あると言えるでしょう。 |
5-2.就職・転職に有利になる
日商簿記2級以上の資格を取得していると、経理や会計の転職・就職で有利になります。
実際に「日本の資格・検定」が実施している「就職に役立つ資格・検定ランキングTOP30」では、3年連続日商簿記検定が1位を取得しています。
参考:日本の資格・検定「2023年版!就職に役立つ資格・検定ランキングTOP30」
就職に役立つと実感している人が多いのはもちろん、企業の採用担当者が日商簿記検定の価値を理解しています。
履歴書に「日商簿記2級取得」と記載していると、差別化のポイントになるでしょう。
【日商簿記2級が就職・転職に役立った声】
また、経理や会計業務では「日商簿記2級以上必須」「日商簿記2級以上優遇」と記載されている求人情報も目立ちます。
中には実務経験がなくても日商簿記2級以上があれば応募できるケースもあり、未経験であっても経理や会計業務に挑戦しやすくなります。
日商簿記2級以上を条件としている企業には税理士事務所や大手企業の経理なども含まれているので、年収アップや就職先・転職先の選択肢の拡大が見込めるでしょう。
| 【日商簿記2級以上を条件にしている転職先・就職先例】 ・税理士補助 ・大手企業の経理 ・監査業務の補助 |
このように、日商簿記2級があると会計や経理に関する専門的なスキルを持ち合わせていると捉えられるので、日商簿記3級よりも圧倒的に転職・就職に有利になると言えるでしょう。
▼日商簿記2級の就職や転職については下記の記事でも触れているので、参考にしてみてください。
【キャリア】簿記2級取得後の年収や就職・転職状況はどうなる?
簿記2級は転職に有利?簿記2級を活かせる職種や転職時期も紹介
| 【日商簿記2級で資格手当が支給されるケースがある】 日商簿記2級は専門的なスキルだとみなされることが多いです。 経理や会計など日商簿記2級のスキルを業務に活用する業種では、 資格手当として1,000~5,000円程度支給されることがあります。 例えば、毎月5,000円の資格手当が支給される場合は、 年間で60,000円、5年で30万円の収入アップにつながります。 |
5-3.大学入試時に優遇されるケースがある
日商簿記2級を取得していると、主に選抜での大学入試時に優遇されるケースがあります。
入試時に優遇を受けられる大学は商工会議所の公式サイトで公表されており、2024年2月時点では市立大学で優遇が受けやすくなっています。
| 大学の種類 | 優遇される内容 | 優遇のある大学数 |
| 国公立大学 | 応募時:資格保有に加え別要件も満たすことで出願資格を獲得 | 7校 |
| 選考時:資格保有により選考時に加点 | 1校 | |
| 私立大学 | 応募時: 資格保有により出願資格を獲得 | 29校 |
| 応募時:資格保有に加え別要件も満たすことで出願資格を獲得 | 41校 | |
| 選考時:資格保有により選考時に加点 | 31校 |
※簿記の対象級について言及がない場合を除きます
※学科や選抜方法により優遇が異なる場合があります
※商工会議所の公式サイトで公表している大学のみで算出しています。詳しい優遇は志望大学にご確認ください
日商簿記3級よりも入試時に優遇を受けられる大学は多く、日商簿記2級の価値を評価していることが分かります。
とくに選考時の加点を受けられる場合は日商簿記2級を取得しているだけで、未取得の志望者に差をつけられます。
あなたの志望大学が日商簿記2級の優遇を用意している場合は、取得しておくと大学入試時に有効活用できるでしょう。
5-4.上位資格を目指しやすくなる
日商簿記2級を取得すると、公認会計士・税理士や日商簿記1級などの上位資格を目指しやすくなります。
日商簿記3級からでも上位資格は目指せますが基礎知識しか習得できていないため、専門的なスキルを身につけるまでに時間がかかります。
| 上位資格の目指しやすさ | |
| 日商簿記2級 | 日商簿記1級や公認会計士・税理士など経理や会計に関する上位資格取得につながりやすい |
| 日商簿記3級 | 簿記の入門資格なので専門的なスキルを身につけるためのスキルアップが必要 |
| 日商簿記1級 | 日商簿記の中での最上位資格なので他の経理や会計に関する上位資格取得につながりやすい税理士資格では受験条件を満たしたことになる |
【日商簿記2級から上位資格を目指す声】
日商簿記2級まで取得してしまえば簿記と経営管理の双方の知識を活かして、日商簿記1級や公認会計士・税理士を目指しやすくなるでしょう。
「将来会計や経理の専門的なスキルを身につけて活躍したい」「公認会計士・税理士などの上位資格に興味がある」という場合には、会計や経理の知識を深めることで将来設計に役立てられます。
6.日商簿記2級のメリットを享受できる人とは?
ここまで解説してきたように、日商簿記2級は会計や経理に関する専門的なスキルを身につけられます。
ビジネスパーソンが持つべきスキルとして幅広い業務で活用できますが、とくに下記のケースは日商簿記2級の取得が向いています。
どのような人が日商簿記2級を最大限に活用できるのか、ぜひチェックしてみてください。
| 日商簿記2級のメリットを享受できる人 |
| ・会計や経理の知識を就職・転職に活かしたい人 ・上位資格取得に向けて知識をつけたい人 ・進学したい大学に簿記2級の優遇がある人 |
6-1.会計や経理の知識を就職・転職に活かしたい人
| こんな人におすすめ |
| ・会計や経理の分野で活躍したい ・会計や経理の分野でスキルアップしたい ・未経験だけれど会計や経理の仕事に転職したい |
日商簿記2級は、会計や経理業界への就職や転職時に評価してもらえる可能性が高い資格です。
「5-2.就職・転職に有利になる」で触れたように、帳簿記入と経営管理の双方のスキルがある証になるからです。
それだけでなく下記のように、日商簿記2級以上を条件にしている企業が一定数あることなど就職や転職に有利な条件が複数揃っています。
| 【日商簿記2級が就職や転職に活用できる理由】 ・帳簿記入と経営管理の双方のスキルがある証になる ・日商簿記2級以上を採用条件・優遇条件にしている企業が一定数ある(3級より多い) ・商業簿記だけでなく工業簿記分野まで業務範囲を広げられる ・未経験でも日商簿記2級以上があることで雇用対象になるケースがある |
また、日商簿記2級があれば会計や経理業務が未経験であっても「業務ができるレベルの知識がある」とみなされるため、就職や転職しやすくなる側面もあります。
【日商簿記2級を取得して未経験から就職した声】
「会計や経理業界で仕事がしたい」「資格を取得して会計や経理業界でスキルアップしたい」という方は簿記2級の取得がおすすめです。
| 【他の資格と組み合わせて活躍できる幅を広げることも可能】 日商簿記2級はFASS検定(経理・財務スキル検定)や、 給与計算実務能力検定などの会計に関する資格と組み合わせて、活躍の幅を広げることができます。 企業によっては担当できる業務が増えるため、昇進や資格手当支給につながる可能性もあります。 「現在経理や会計に関する業務に携わっている」「関連資格を取得している」という場合でも、 日商簿記2級を取得してキャリアアップを目指すことも可能です。 |
6-2.上位資格取得に向けて知識をつけたい人
| こんな人におすすめ |
| ・日商簿記1級や公認会計士 ・税理士などの上位資格を目指したい ・上位資格取得に向けて知識を身につけたい |
将来日商簿記1級や公認会計士・税理士などの上位資格を取得したい場合にも、日商簿記2級の取得がおすすめです。
日商簿記1級は2級を飛ばして挑戦できますが、日商簿記2級を理解していないと日商簿記1級には合格できません。
日商簿記2級を取得してから1級に挑戦するのが一般的なので、上位資格を目指すためにはまずは日商簿記2級を取得することが重要です。
例えば公認会計士試験では、試験科目のうち2つは会計科目(財務会計論、管理会計論)です。これらは、日商簿記2級の商業簿記と工業簿記の内容が基礎となっているため、簿記2級の知識は公認会計士試験の学習を進めるうえで非常に役に立ちます。
また、税理士試験には、簿記論という科目があります。日商簿記2級を取得していると約60%、1級を取得していると約90%が学習済みとなるので、税理士試験を目指すときに有利に勉強ができます。
このように「上位資格を狙いたい」という明確な目標がある場合は、日商簿記2級を取得しておくと次のステップに進みやすくなります。
| 【公認会計士は公認会計士試験勉強から開始することがおすすめ】 日商簿記2級の内容は公認会計士試験の勉強に役立つと述べましたが、 一般的には公認会計士を目指している場合は、 目標としている公認会計士試験まで充分な時間がある場合を除き、 公認会計士試験の勉強から始めたほうがいいと言われています。 なぜなら、公認会計士試験勉強の中で日商簿記3~1級の内容を学んでいくからです。 既に日商簿記2級を取得している場合は知識が役に立ちますが、 一から日商簿記2級に取り組むと公認会計士試験までに時間と労力がかかります。 公認会計士試験勉強と日商簿記2級勉強で重複する部分も多いので、 公認会計士を目指すなら公認会計士の勉強に集中することをおすすめします。 |
6-3.進学したい大学に簿記2級の優遇がある人
| こんな人におすすめ |
| ・進学したい大学に日商簿記2級の優遇がある ・入試時に他の学生と差別化できるポイントを作っておきたい |
あなたが進学したい大学に日商簿記2級の優遇がある場合は、アピールポイントとして日商簿記2級の取得を狙うといいでしょう。
「5-3.大学入試時に優遇されるケースがある」でも触れましたが、日商簿記2級になると優遇を用意している大学が一気に増えます。
とくに市立大学の経営学部や経済学部、商学部の選抜入試に優遇が多い傾向があります。
優遇の内容は大学により異なりますが、選考時の加点や応募要件の獲得につながる場合もあるので無資格の学生よりも有利になるでしょう。
「大学入試時に何らかのアピールポイントを持っておきたい」「大学入学後にも役立つ資格を取得したい」という場合は、日商簿記2級にチャレンジする価値があります。
7.【2024年】日商簿記2級の試験方法・日程
ここまでこの記事を読み、日商簿記2級を取得してみようと思ったら、気になるのが試験の日程や方法ですよね。
日商簿記2級は「統一試験」「ネット試験」「団体試験」の3つの試験方法があり、それぞれ日程や実施場所が異なります。
日商簿記2級を受験しようとしたときに迷わないためにも、事前に各試験方法について詳細を把握しておきましょう。
| 統一試験 | ネット試験 | 団体試験 | |
| 解答方法 | 紙の解答用紙に記入する | パソコンに入力する | 紙の解答用紙に記入する |
| 回数 | 1年に3回 | 会場により異なるが統一試験より多い | 申請する団体により異なる |
| 実施場所 | 申込先の商工会議所が指定する全国の試験会場 | 全国のテストセンター | 企業や学校が指定する会場 |
| 合否 | 2~3週間程度かかる | その場で分かる | 2~3週間程度かかる |
| 受験料 | 5,500円(税込) | 5,500円(税込)※別途事務手数料あり | 5,500円(税込) |
| 合格証 | 紙の合格証 | デジタル合格証 | 紙の合格証 |
7-1.統一試験の日程
統一試験は、指定された試験会場に足を運び紙面の解答用紙に答えを記入する方法です。
学校の期末試験などと同様に、紙面の問題を見ながら紙面の解答用紙に答えを記入する試験だと考えると分かりやすいでしょう。
※東京商工会議所など一部の商工会議所では統一試験が廃止され、ネット試験のみになっています。
統一試験はネット試験のパソコン操作に不安がある場合や、臨場感のある試験会場で受験したい場合に向いています。
| 項目 | 概要 |
| 向いているケース | ・パソコン操作に不安がある場合 ・臨場感のある会場で集中して取り組みたい場合 ・紙面への記入に慣れている場合 |
| 注意点 | ・結果発表までに2~3週間程度時間がかかる ・商工会議所により申し込み方法や締切日が異なる |
一方で、結果発表までに約2~3週間かかるので「就職活動が迫っていてすぐに結果が知りたい」「すぐに合格証明書を受け取りたい」という場合は、ネット試験を選択しましょう。
統一試験は、1年に3回開催されます。
2024~2025年の実施スケジュールは下記のとおりです。
| 2024年~2025年の日商簿記2級試験日 | |
| 第167回 | 2024年6月9日(日) |
| 第168回 | 2024年11月17日(日) |
| 第169回 | 2025年2月23日(日) |
統一試験の開催場所や申込受付日時、申込受付方法は商工会議所ごとに異なります。
日商簿記2級を受験したい地域の商工会議所の指示に従って申し込みをしてください。
一例として千葉県の商工会議所の申し込み手順を見てみましょう。
①商工会議所検索ページで「千葉」を選択します。
出典:日本商工会議所公式サイト
②「簿記」に〇マークのついている商工会議所を選びます。今回は「船橋商工会議所」を選択します。
出典:日本商工会議所公式サイト
③船橋商工会議所で実施している日商簿記検定と基本情報が表示されます。
実施場所の住所を確認し問題なければ、2級のインターネット申し込みをクリックして申し込みに進みます。
出典:日本商工会議所公式サイト
このように、事前に受験したい地域の商工会議所の指示に従って手続きを済ませておきましょう。
7-2.ネット試験の日程
ネット試験は、全国のテストセンターに出向きパソコンを使って解答する方法です。
テストセンターでA4用紙2枚と筆記具(ボールペン)が配布されるので、用紙を使い計算をしながら解答をパソコン画面に入力します。
ネット試験は統一試験よりも頻繫に実施しているので、自分のタイミングで試験を受けたい人におすすめです。
統一試験のように年3回の試験日を待たなくても、試験が受けられると思ったタイミングでチャレンジすることが可能です。
また、ネット試験はその場で合否が分かります。
日商簿記2級に受験回数制限はないので、不合格だった場合にすぐに再チャレンジできる点もメリットです。
例えば、合格を急いでいるときに不合格だった場合、空きさえあれば翌週に再試験を受けることも可能です。
| 項目 | 概要 |
| 向いているケース | ・自分のタイミングで受験したい場合 ・パソコン操作に抵抗がない場合 ・すぐに合否を知りたい場合 |
| 注意点 | ・統一試験とは申し込みの手順が異なる ・パソコン操作に慣れている必要がある |
ネット試験の試験日は、テストセンターにより異なります。
試験を受けたい地域のテストセンターを事前に確認して、受験予約をしましょう。
| 【試験日】 全国のネット試験会場が決める(統一試験よりも回数が多い) ※全センター共通の休止期間 ・2024年4月1日~4月13日 ・2024年6月3日~6月12日 ・2024年11月11日~11月20日 ・2025年2月17日~2月26日 |
参考:日本商工会議所「日商簿記検定試験(2級・3級)ネット試験について」
一例として東京都でのネット試験予約の手順をご紹介します。
①ネット試験会場ページで「東京」をクリックします。
出典:日本商工会議所公式サイト
②東京都内のテストセンターが一覧表示されるので、日商簿記2級に対応している最寄りのテストセンターを探します。
日商簿記2級を受けたいテストセンターが見つかったら「簿記受付」をクリックします。
出典:日本商工会議所公式サイト
③日商簿記検定の受験者専用サイトに移行するため、会員登録をして受けたい受験の予約を行います。
このように、ネット試験は受験したいテストセンターを探して受験者専用サイトから登録・申し込みをする必要があります。
また、ネット試験では受験料とは別に事務手数料が発生するので、支払いをする際に注意してください。
▼ネット試験の注意点やメリットは下記の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。
簿記2級のネット試験について解説!統一試験との違いや注意すべきこと
7-3.団体試験の日程
団体試験とは、企業や学校などの団体でまとめて日商簿記2級の受験申し込みをする方法です。
受験形式は統一試験と同じで、指定の会場に出向いて会場で配布された問題用紙と解答用紙を使い解答します。
団体試験は企業や学校が窓口となり受験の取りまとめをして、商工会議所に申込みします。
個人で受験準備をする手間が省ける点が大きなメリットです。
また、基本的には申し込みをした企業・学校の従業員や学生が対象となるため、一緒に日商簿記2級を目指す仲間が見つかる可能性もあるでしょう。
| 項目 | 概要 |
| 向いているケース | ・企業や学校が団体試験を実施している場合 ・試験申し込みの準備負担を軽減したい場合 ・企業や学校内で日商簿記2級を目指せる仲間を見つけたい場合 |
| 注意点 | ・企業や学校が実施していないと選択できない |
団体試験の会場や試験日は商工会議所と調整して決めるので、都度確認するようにしてください。
| 【試験日】 企業や学校などの団体と商工会議所が調整して決める |
参考:日本商工会議所「日商簿記検定試験(団体試験方式)の施行開始について【企業・教育機関関係者様】」
また、団体試験は企業や学校などの団体が商工会議所に申請をしないと選択できない方法です。
どの企業や学校でも実施しているわけではないので、あなたの所属する学校や企業が対応しているか確認しておくといいでしょう。
8.日商簿記2級合格に必要な勉強時間は250時間程度
ここまで、日商簿記2級の概要や取得メリットを解説してきました。
入門資格の日商簿記3級より一歩踏み込んだ専門的なスキルを身につけられる日商簿記2級に、魅力を感じた方は多いでしょう。
いざ日商簿記2級の勉強を始めようとするときに気になるのが、勉強時間ですよね。
日商簿記2級合格に必要な勉強時間は、250時間程度が目安です。
1日2時間試験勉強をした場合には、約4ヶ月で合格を目指せます。
半年以内に合格できる可能性があるので、学校や仕事とも両立しやすく無理なく試験勉強を継続しやすいでしょう。
一例として、社会人と学生の勉強スケジュールを見てみましょう。
社会人は平日の仕事が終わってから1.5~2時間程度、休日は進捗状況に応じて2.5~3時間程度の勉強時間を確保できれば効率よく試験勉強を進められます。
日商簿記2級の勉強はアウトプットとインプットのバランスが大切なので、平日はテキストを読みインプットをする、週末で過去問や苦手な問題を解くなどメリハリをつける取り組み方もおすすめです。
資格学校に通う場合は資格学校のスケジュールに合わせる必要がありますが、資格学校以外でも勉強する時間を設けるようにしましょう。
高校生の場合は、下記のように学校の勉強とは別に日商簿記2級の勉強をする時間を取ることが大切です。
平日は学校からの帰宅後に、休日はバイトや部活とのバランスを見ながら時間を取るといいでしょう。
このように、日商簿記2級は難易度が高いものの、半年程度コツコツと勉強できれば十分に合格を目指せます。
▼日商簿記2級の合格に必要ば勉強時間は下記の記事でも解説しているので、参考にしてみてください
簿記2級の合格に必要な勉強時間やおすすめの勉強方法を徹底解説!
8-1.日商簿記2級は独学でも目指せる
日商簿記2級は難易度が高いものの、コツコツと継続して試験勉強ができれば独学でも合格を目指せます。
実際に独学で合格できた声も多数あります。
【日商簿記2級に独学で合格した声】
日商簿記2級に独学で合格するポイントは、次のとおりです。
| 【日商簿記2級に独学で合格するポイント】 ・理解できないところは3級まで戻り基礎固めをする ・暗記だけに頼るのではなく「なぜそうなるのか」という根本的な理解をする ・「絶対に合格する」強い意志を持ちコツコツと勉強する ・理解しきれない部分はeラーニングや複数のテキストを活用する |
日商簿記2級は基礎知識に加え応用知識が必要なので、暗記だけに頼らず「なぜそうなるのか」という根本的な理解を怠らないようにしましょう。
分からない部分は日商簿記3級の出題範囲まで戻り、納得できるように基礎知識をしっかりと固めることが重要です。
それでも「テキストを読んだだけでは分からない」「本当に自分の理解が合っているのか不安」という場合には、無料で利用できる「CPAラーニングの簿記講座」を活用してみてください。

CPAラーニングは、簿記や経理実務など1,500本以上の講義を無料で視聴できるeラーニングサイトです。
2級講義の講義動画やテキスト、模擬試験などを無料で利用でき、独学での合格を徹底的にサポートします。
とくに講義は公認会計士またはプロの実務家が担当しているので、日商簿記2級の学習内容について理解できるようになります。
「CPAラーニングの簿記講座」はメールアドレスの登録のみですぐに全コンテンツが使用できるため、日商簿記2級の試験勉強にぜひ利用してみてください。
9.日商簿記2級の出題傾向と学習のポイント
日商簿記2級は「3.日商簿記2級の試験範囲一覧」で解説した試験範囲を5問に分けて出題します。
下記のように第1問から第5問まで出題内容が異なるので、どのように学習するべきか迷うところですよね。
ここでは、大問ごとの学習ポイントをご紹介します。
日商簿記2級合格を目指して勉強するときの参考にしてみてください。
| 【日商簿記2級の大問を解く順序は?】 日商簿記2級は90分以内に解答する必要があるため、 どの大問から取り掛かればいいのか気になるところですよね。 結論から言うと、大問を解く順序に決まりはありません。 得意分野から取り掛かってもいいですし、分かる問題から解いても問題ありません。 一例としておすすめの順序は、下記のとおりです。 解きやすい大問から挑戦し、時間のかかる大問は後半にじっくりと向き合うといいでしょう。 |

9-1.仕訳:問題の形式に慣れる
仕訳問題は、日々の取引を帳簿記録する知識を確認する問題です。
会計や経理の基礎となる問題なので、ルールを理解してスピーディーに解答できるよう練習しましょう。
仕訳問題を解くときのポイントは、問題形式に慣れておくことです。
日商簿記2級の仕訳問題は問題文が長く、日本語が複雑で理解しにくい傾向があります。
問題に慣れていないと意図や概要を掴めず、解答に時間がかかってしまいます。
商業簿記と工業簿記の仕訳の基礎知識が理解できたら、積極的に問題集や過去問を使い問題に慣れる練習をしてみましょう。
| 【仕訳問題例】 かねて仕入先から掛けで購入した甲商品100個(@¥2,000)について、 1個当たり¥100の支払いを免除される旨の通知を受けたため、 当該免除額を差し引いた残額について小切手を振り出して支払った。 ア. 売上原価 イ. 売 上 ウ. 買掛金 エ. 当座預金 オ. 売掛金 カ. 仕 入 |
9-2.個別論点:体系的な深い理解が必要
個別論点は、特定の論点を深く掘り下げる問題です。
株主資本等変動計算書や連結精算表などの出題頻度が高く、体系的に理解をして読み解けるようにしておきましょう。
このときに丸暗記をすると、株主資本等変動計算書や連結精算表などを記録する意味を理解できなくなってしまいます。
仕訳を覚えることは重要ですが、記録する意味・目的も理解するためにも、基礎知識をしっかりと身につけましょう。
実際に自分で記録する機会を増やすために、繰り返し練習問題を解いてみることもおすすめです。
また、個別論点は問題を理解して解答するのに一定の時間を要するため、最後に解くと余った時間を使いじっくりと考えることができます。
9-3.総合問題:正確にスピード感を持ち解けるようにする
総合問題は、財務諸表や精算表など決算に関する理解を確認する問題です。
総合問題の流れは基本的には変わらないため、基礎をしっかりと押さえてスピーディーに解答できるようにしましょう。
総合問題では、下記の問題が出題される傾向があります。
問題によって傾向を理解して、対策をするといいでしょう。
| 問題 | 概要 |
| 貸借対照表・損益計算書の作成 | 決算整理事項等による変動が財務諸表にどのような影響を及ぼすのか判断し、スピーディーに処理する |
| 未処理事項に関する問題 | 未処理事項で変動した金額が決算整理事項に影響を与えるパターンが定番難易度が高くなる傾向があるので部分点を狙い正確に解答する |
決算問題で考え込んでしまうと他の問題を解く時間がなくなってしなうので、頭の中で仕訳をイメージしながら効率よく問題を解けるように練習しましょう。
9-4.工業簿記:計算に慣れておく
第4問と第5問は工業簿記分野からの問題です。基本的な問題が多く、難易度が比較的低いので満点を目指したい大問です。
| 仕訳/計算問題 | 仕訳問題3つと個別原価計算・総合原価計算が出題される傾向があるどれも基礎的な問題なので基礎固めをして満点を狙う |
| 原価計算 | 直接原価計算・標準原価計算が出題される傾向がある練習問題を繰り返し解いて正確に解答できるようにする |
どちらも基礎的な問題が中心なので、繰り返し練習問題を解いて計算問題に慣れておくようにしましょう。
とくに、原価計算の場合は公式や図に頼り過ぎず、過程を理解して解くことが大切です。
理解度を確認するために、ボックス図やシュラッター図を書かずに問題を解いてみるのもおすすめです。
このように、日商簿記2級の試験勉強は基礎をしっかりと押さえながら練習問題にチャレンジして問題を解くことに慣れるようにしましょう。
| 【日商簿記2級の試験勉強におすすめの記事】 日商簿記2級の試験勉強方法についてもっと詳しく知りたい場合は、 下記の記事も参考にしてみてください。 ▼日商簿記2級の試験勉強の始め方を理解しよう 【公認会計士が教える!】日商簿記2級学習の始め方 ▼日商簿記2級の大問ごとの対策方法をチェックしよう 【ネット試験】日商簿記検定2級大問ごとの対策方法 ▼日商簿記2級のテキスト選びをしてみよう 簿記2級のおすすめテキスト15選!無料で利用できるテキストも紹介 ▼日商簿記2級の試験勉強を諦める前に!試験勉強のコツを押さえよう 簿記2級に受かる気がしない…と思っても諦める前にやってほしい試験対策! |
10.まとめ
今回は、日商簿記2級の難易度や出願範囲、試験方法など日商簿記2級の基礎知識をまとめてご紹介しました。
最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。
〇日商簿記2級とは商業簿記と工業簿記の両方を学び企業の財務諸表作成・経営管理ができる知識を身につける資格
〇日商簿記2級の平均合格率は約30%で比較的難易度が高い
〇簿記2級の試験範囲は「商業簿記」と「工業簿記」で帳簿記入と経営管理の知識を身につける
〇日商簿記2級を取得するメリットは次の4つ
1)会計や経理の実務に活用できる
2)就職・転職に有利になる
3)大学入試時に優遇されるケースがある
4)上位資格を目指しやすくなる
〇日商簿記2級のメリットを享受できるのは下記のケース
1)会計や経理の知識を就職・転職に活かしたい人
2)位資格取得に向けて知識をつけたい人
3)進学したい大学に簿記2級での優遇がある人
〇日商簿記2級の受験方法は次の3つ
| 統一試験 | ネット試験 | 団体試験 | |
| 解答方法 | 紙の解答用紙に記入する | パソコンに入力する | 紙の解答用紙に記入する |
| 回数 | 1年に3回 | 会場により異なるが統一試験より多い | 申請する団体により異なる |
| 実施場所 | 申込先の商工会議所が指定する全国の試験会場 | 全国のテストセンター | 企業や学校が指定する会場 |
| 合否 | 2~3週間程度かかる | その場で分かる | 2~3週間程度かかる |
〇日商簿記2級合格に必要な勉強時間は250時間程度
〇日商簿記2級の学習のポイントは下記のとおり
1)仕訳:問題の形式に慣れる
2)個別論点:体系的な深い理解が必要
3)総合問題:正確にスピード感を持ち解けるようにする
4)工業簿記:計算に慣れておく
日商簿記2級は会計や経理の専門的なスキルを身につけられる資格です。
これからさらなるスキルアップを目指したい方は、まず日商簿記2級の学習から始めてみてはいかがでしょうか。